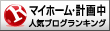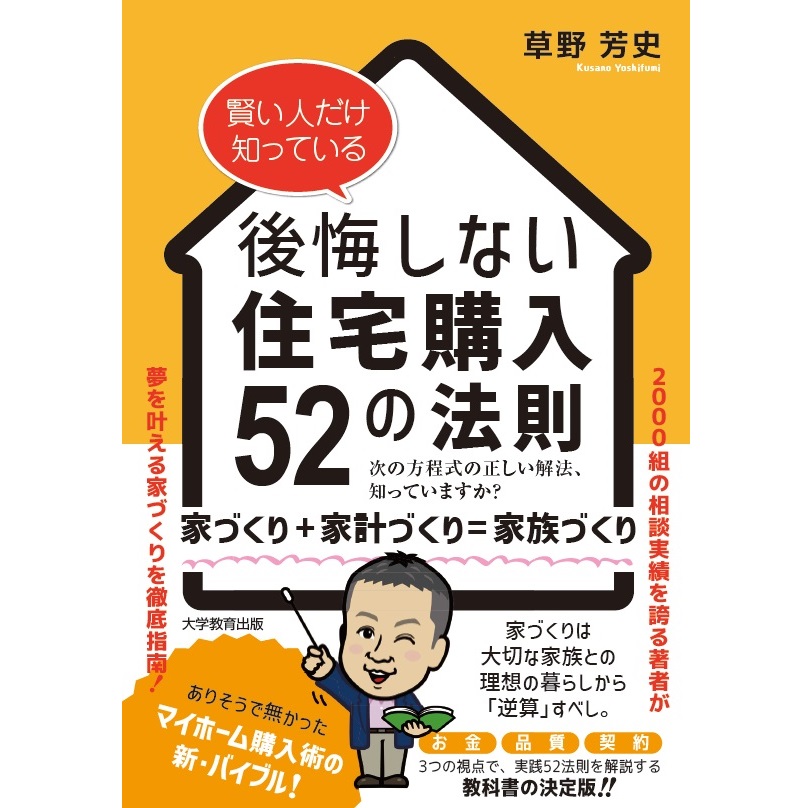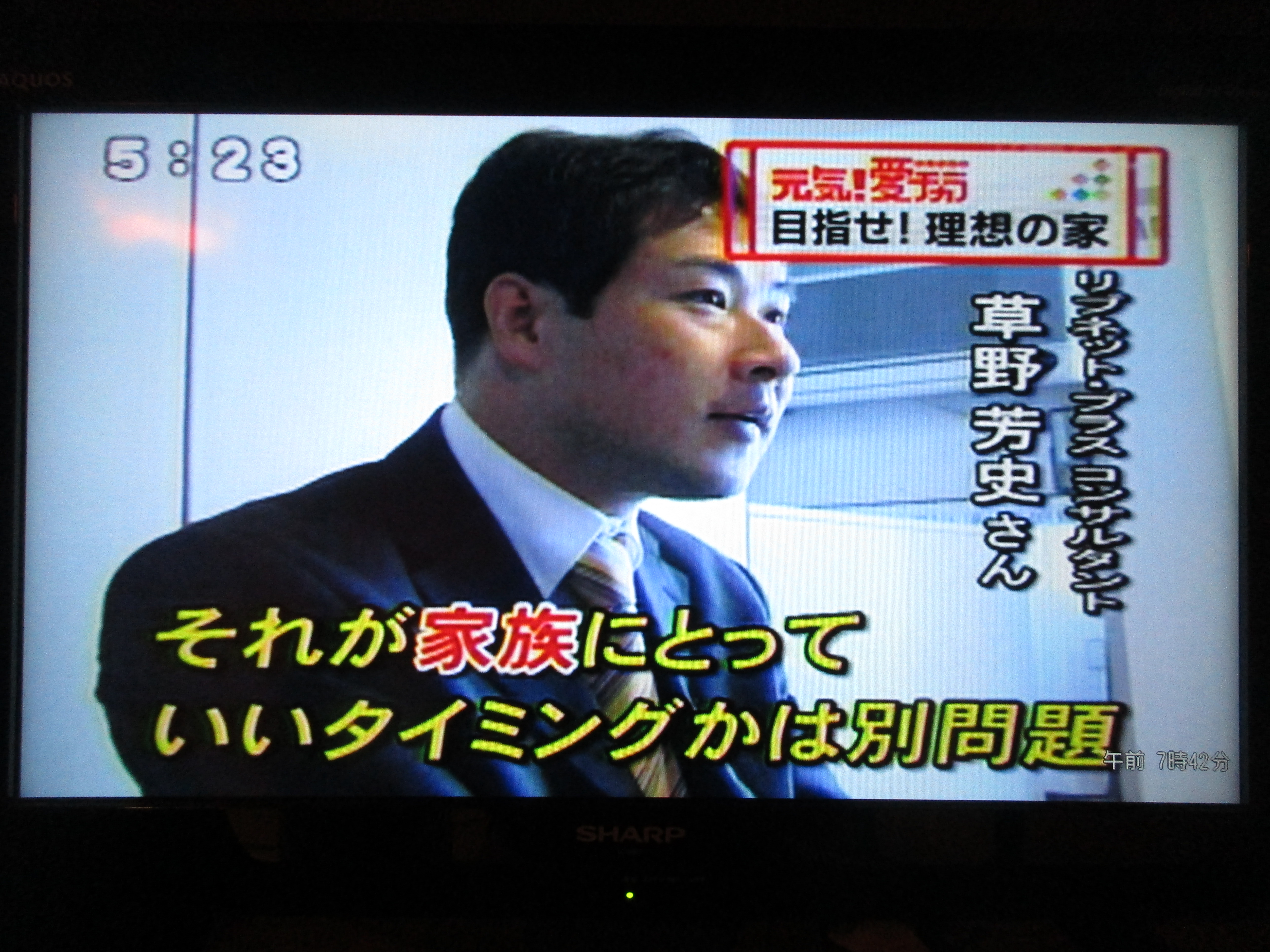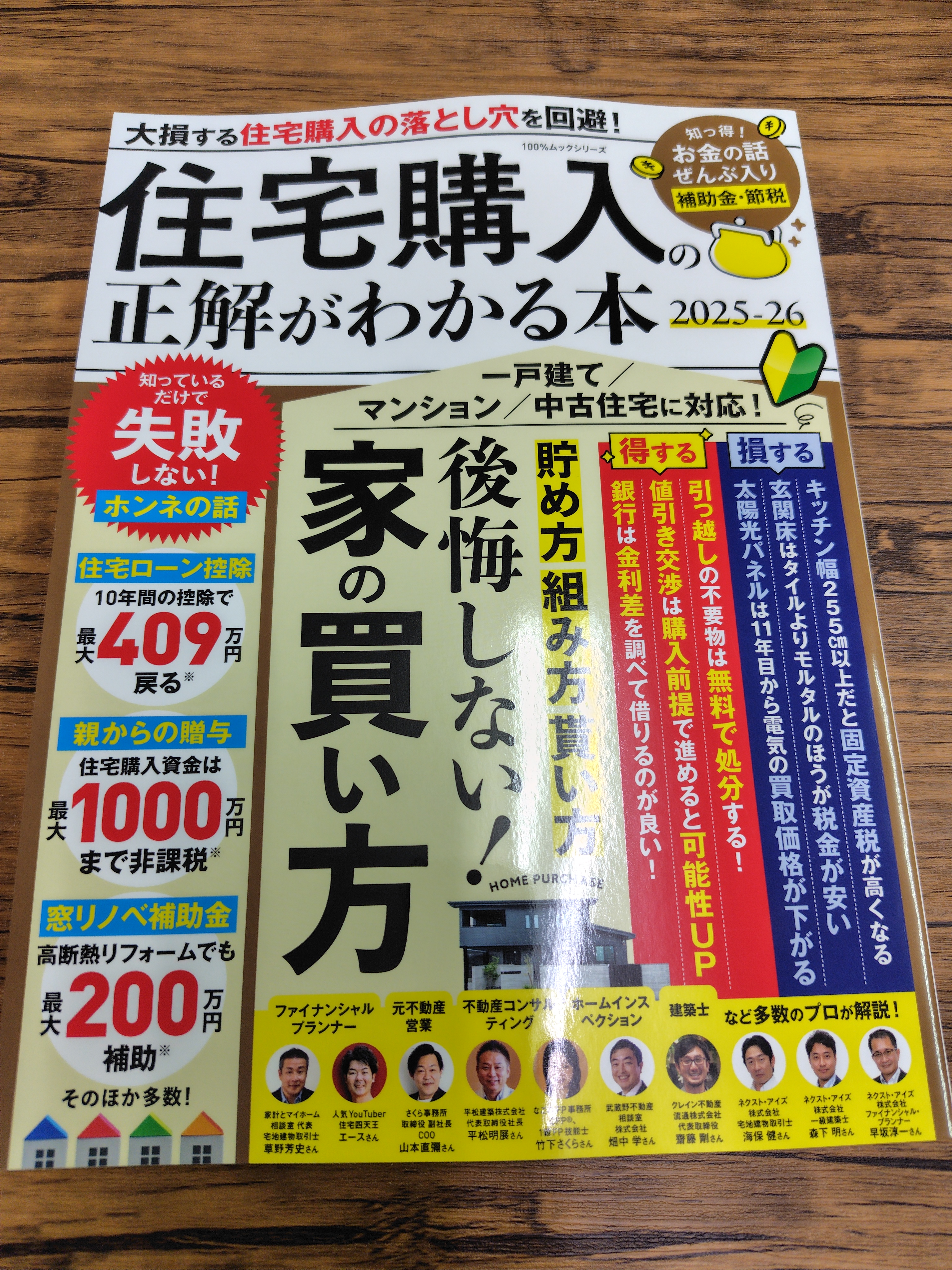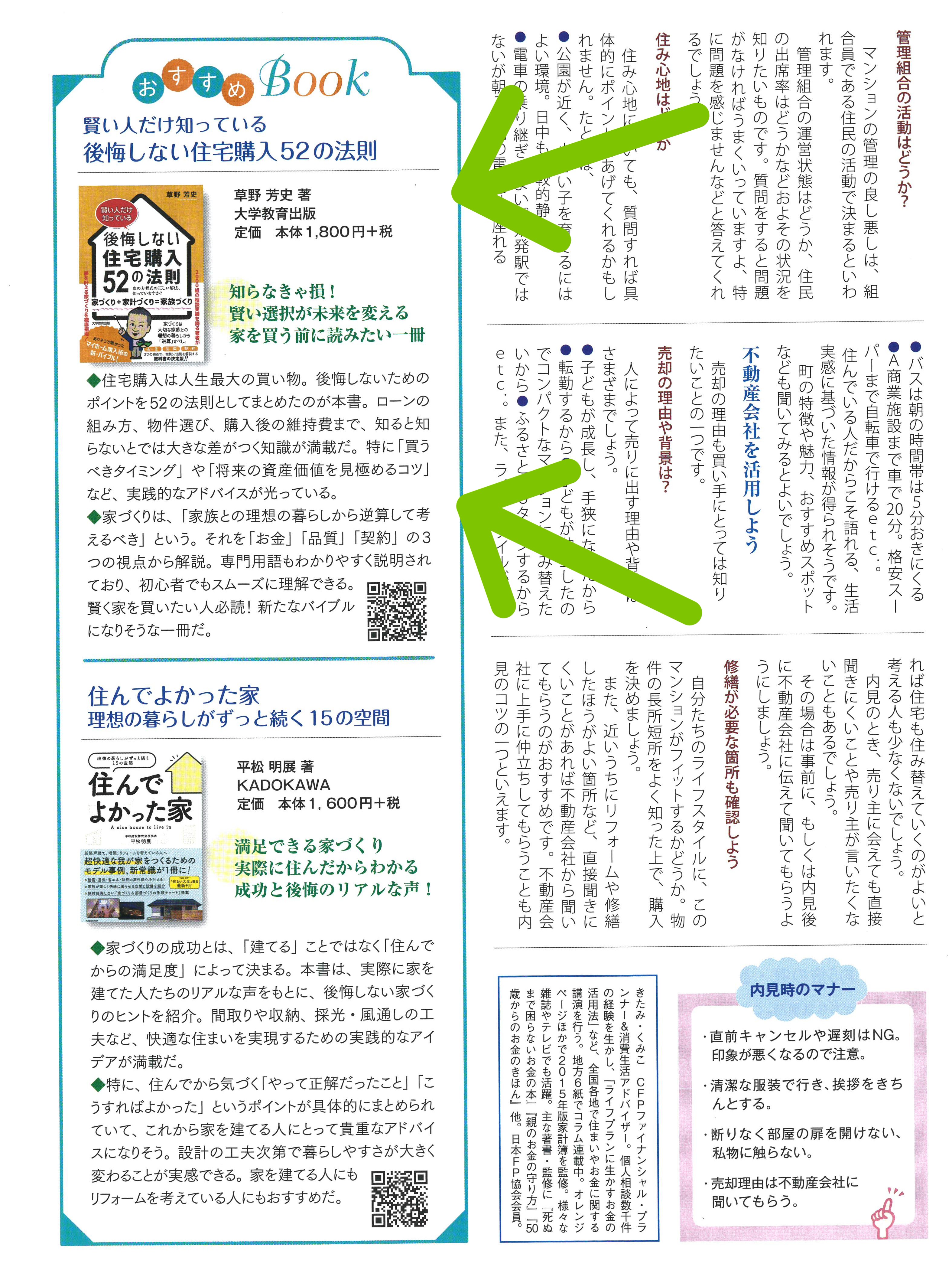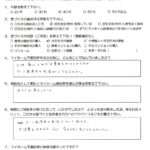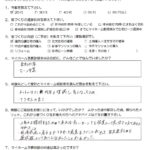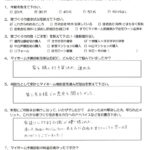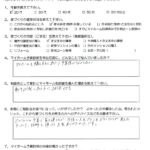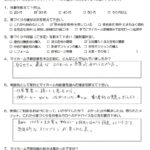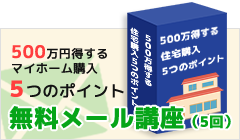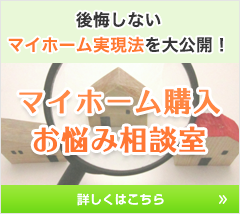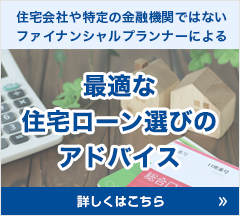公明党の連立離脱や、日本維新の会の閣外協力など紆余曲折を経て10月21日、ついに日本憲政史上初の女性首相――高市早苗内閣が発足しました。政治的な混乱の後だけに、国民の期待と注目は高く、「経済を立て直してほしい」「物価高を何とかしてほしい」そんな声が多く聞かれます。
一方で、家づくりや住宅ローンを考えている方にとっては、この新政権が“金利”にどんな影響を及ぼすのかが最大の関心ごとではないでしょうか。そこで、FPの視点から、高市早苗内閣発足の住宅ローン金利への影響を解説してみたいと思います。
解説①:経済政策は「成長と賃上げ」重視、金融は“慎重姿勢”
高市新首相は就任会見(10月21日)で、「2%の物価目標は、賃上げに裏打ちされた形で達成を」と述べ、物価上昇よりも賃金上昇を伴う持続的成長を重視する姿勢を示しました。これは、金融引き締めに慎重で、急な利上げを望まないメッセージと受け止められています。
財務相には片山さつき氏が起用され、「円の過度な下落を警戒するが、財政拡大には前向き」とされる人物。つまり、“財政は緩く・金融は慎重”という布陣と考えられます。
解説②:市場は「株高・円安・長期金利小幅低下」で反応
高市政権発足を受け、
- 日経平均株価は 49,316円06銭まで上昇(過去最高)
- 為替は 1ドル=151円台まで円安が進行
- 長期金利(10年国債利回り)は 1.66% → 1.61%前後へ小幅低下
という動きになりました。
株価上昇は「経済対策期待」。金利低下は「日銀が当面、利上げを急がない」という見方。つまり、財政拡大×金融緩和維持という政策期待が同時に働いているわけです。
解説③:ただし、円安が続けば“金利上昇圧力”は避けられない
一方で気になるのが、急速に進む円安。円安は、輸入物価を押し上げ、生活コストや建築資材価格にも波及します。私はこの点に注目しています。円安による物価上昇が続けば、日銀としても金利差を縮める方向(=利上げ)に舵を切らざるを得ないでしょう。つまり、「円安が進めば進むほど、遅れて“金利上昇”がやってくる」という構図が見えてきます。
来週(10月29~30日)の日銀・金融政策決定会合では、政策金利(現在0.5%)の引上げこそ見送られる公算が大きいものの、声明文や展望レポートで“次の一手”のヒントが出る可能性があります。
具体的な見通し:住宅ローン金利はこう動く!
ここからが、住宅ローン利用者にとっての本題です。
- 長期固定金利(フラット35など)
長期金利(日本の10年モノ国債利回り)がやや下がっているため、11月の金利は据え置き~わずかに低下する可能性があります。ただし、財政拡大や円安進行が続けば再上昇もあり得るため、“一時的な動き”と見るのが妥当です。
- 変動金利タイプ
仮に来週の日銀会合で政策金利引上げが決まったとしても、各銀行の短期プライムレート(変動金利の基準)は実際に動くまで1~2か月のタイムラグがあります。そのため、変動金利の上昇は早くて年明け以降、遅ければ来春になるでしょう。
————————————————————
行動提案:今、住宅ローンをどう考えるか
————————————————————
- 固定金利で借りる方は、金利ロックを早めに。
11月は一時的に金利が下がる可能性があります。フラット35や全期間固定を検討中なら、事前審査~実行時期を確認し、金利引下げの波に乗るチャンスです。 - 変動金利の方は、返済余力を点検。
年明け~来春にかけての上昇を想定し、キャッシュフロー表で「金利+1.0%」でも返済が続けられるかを確認。 - 為替・物価の影響も要チェック。
円安による建築費上昇や生活コスト増も、家計にじわじわ効いてきます。「家計の将来予測地図」を更新して、無理のない資金計画を立てましょう。
まとめ:株高でも油断禁物、“静かな利上げ”の波を読む
高市内閣は、華々しい船出とともに「期待と不安」を背負っています。経済対策で景気を支えようとする一方で、円安と物価上昇が進めば、日銀は金利引上げで応えるしかありません。短期的には固定金利が下がる局面もありそうですが、大きな流れとしては「金利上昇への備え」が必要です。マイホーム計画は、“今の金利水準”に安心せず、来年以降の利上げ局面を見据えた資金設計をしていきましょう。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□