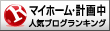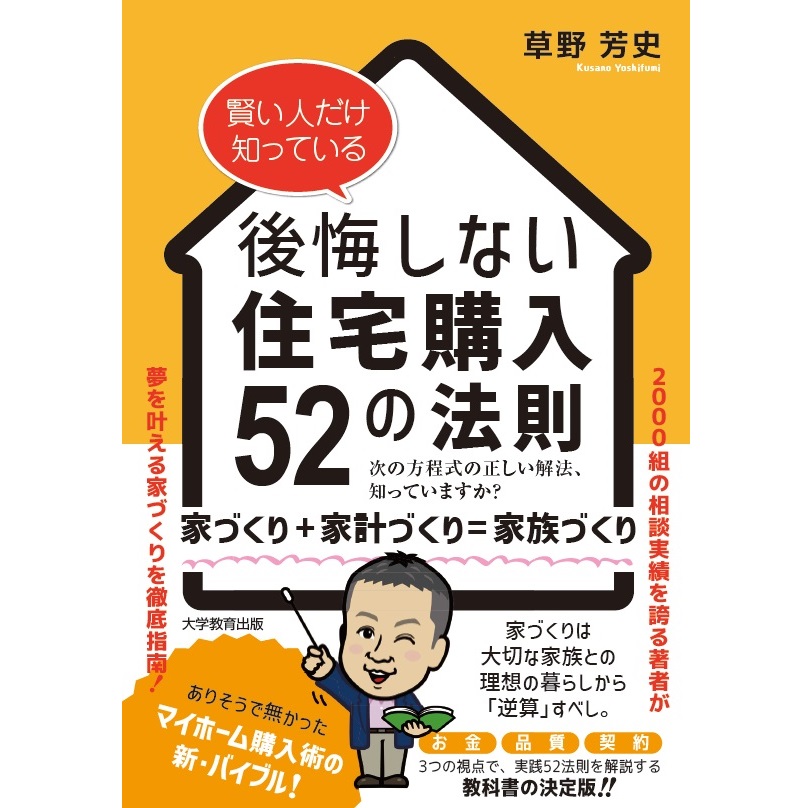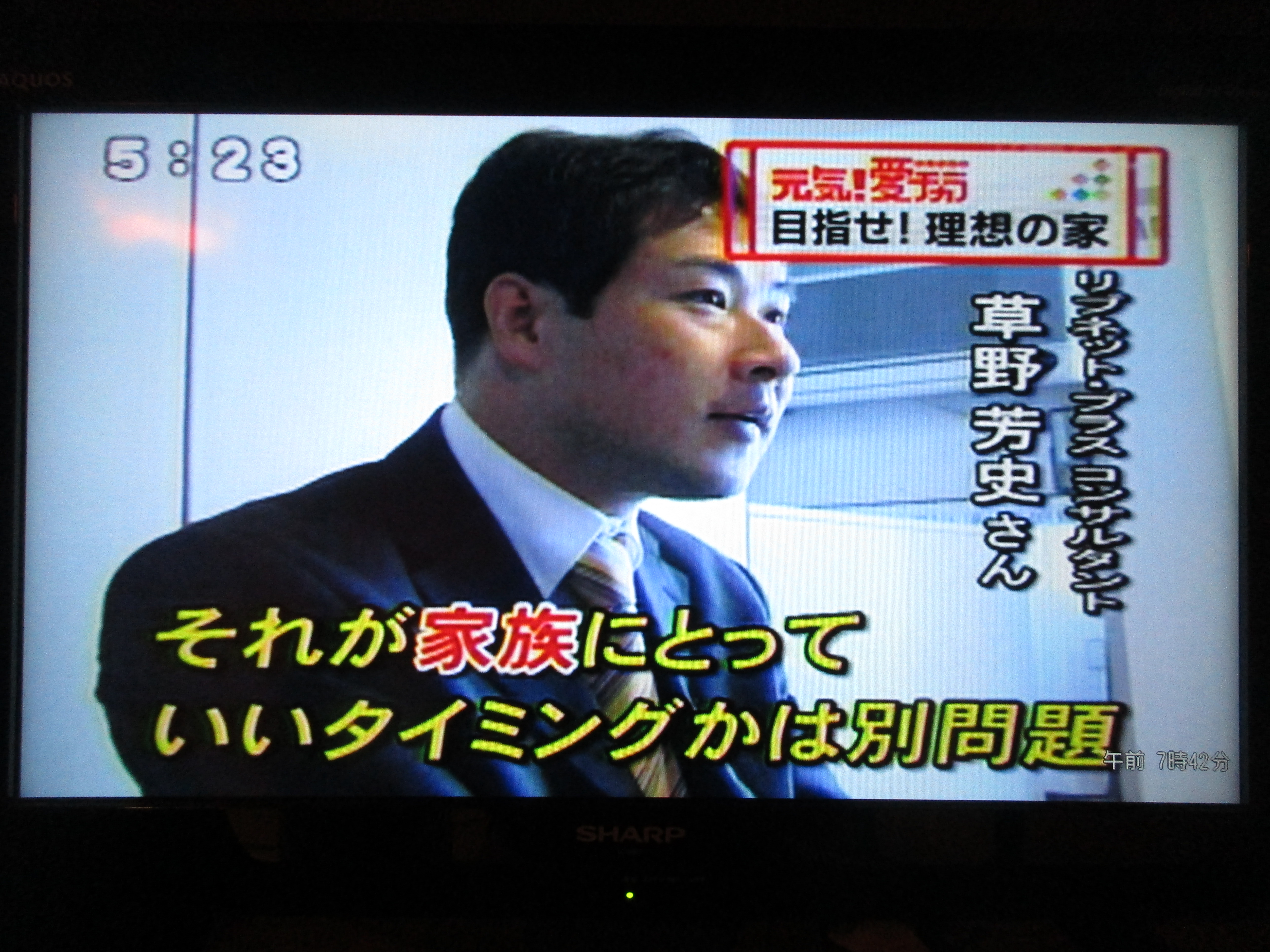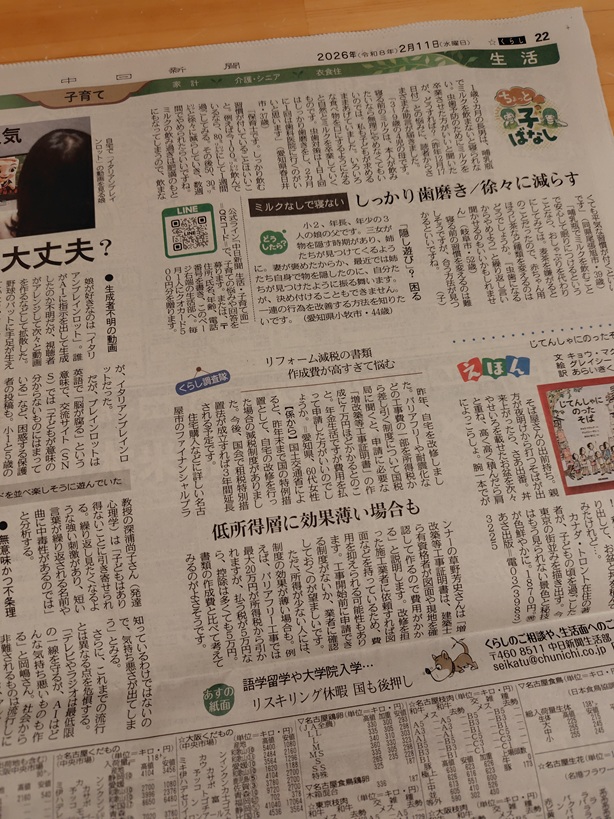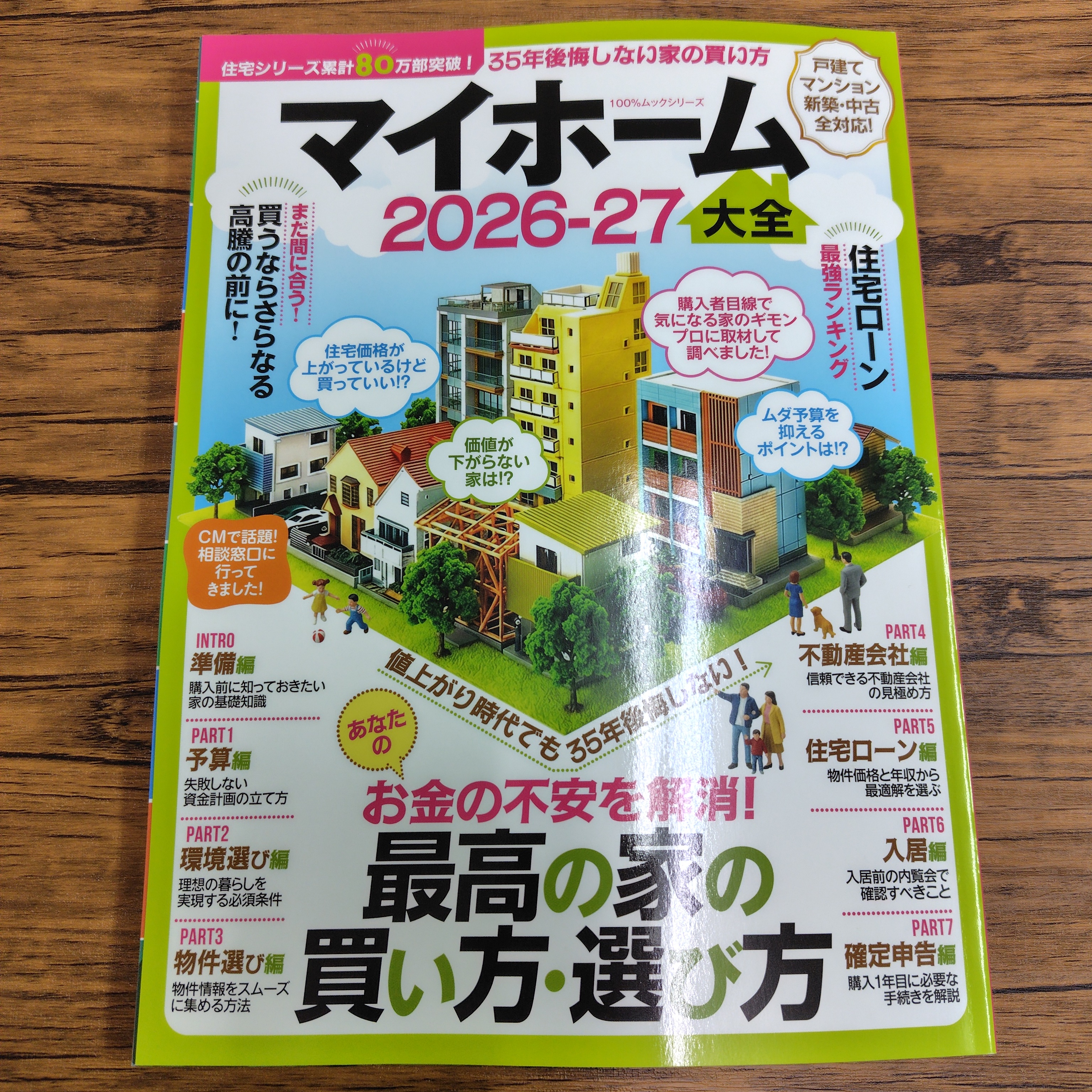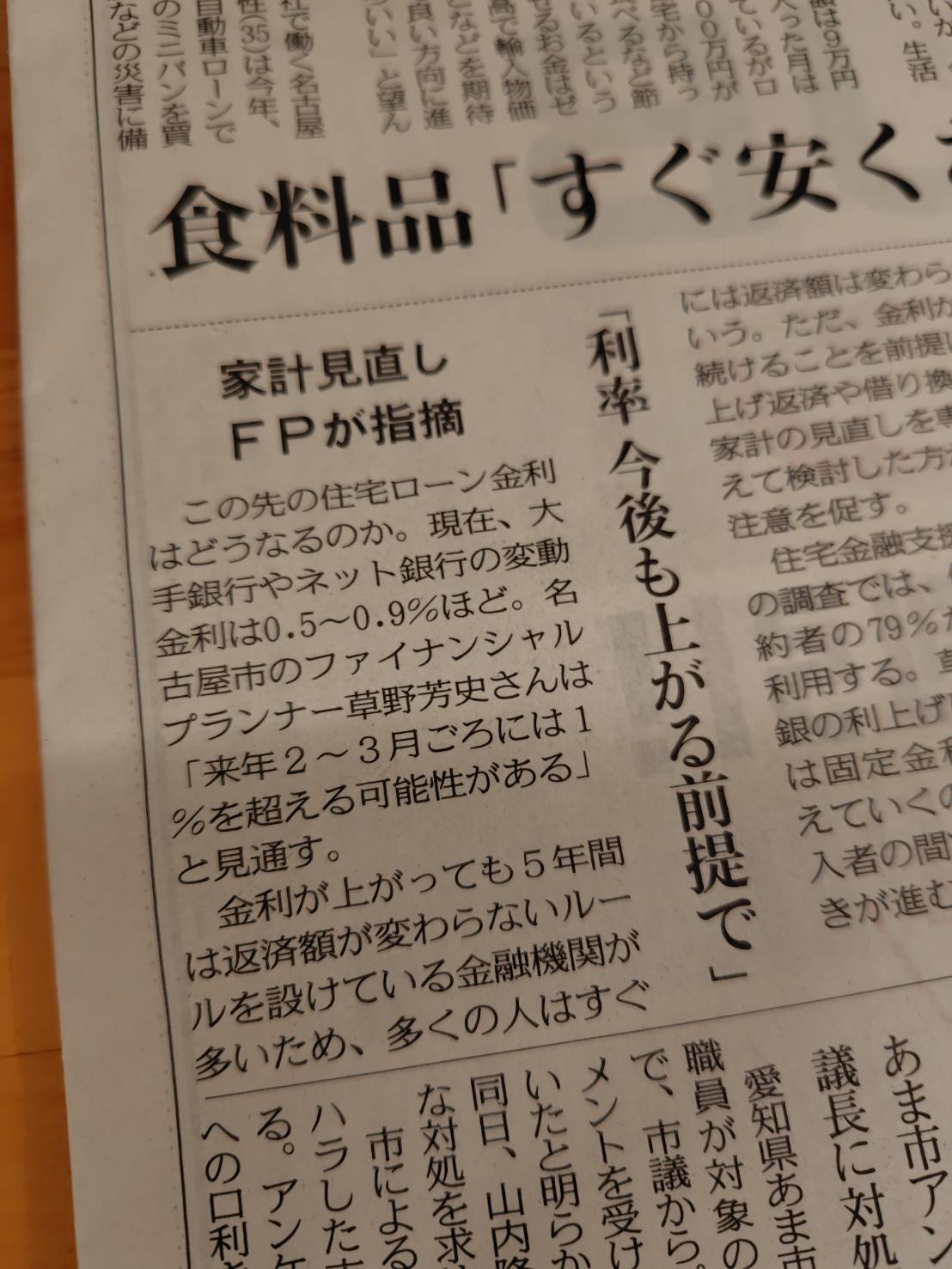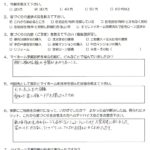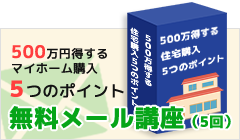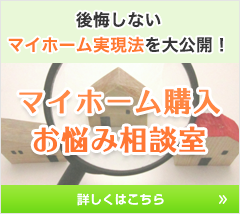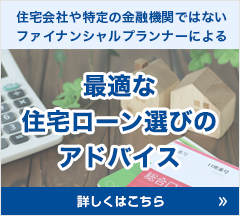住宅ローンの金利が上がるなか、将来の金利上昇リスクを抑えたいと、固定金利タイプを選ぶ方が増えています。その有力な候補がフラット35。わたくし草野のご相談者でも、このところフラット35をご提案するケースが増えています。フラット35Sや子育てプラスといった金利優遇が使えるほか、利上げが進む民間金融機関の固定金利タイプに比べて割安だからです。
そんな中、フラット35に関して新たな動きがありました。昨日、新聞・ネットなど各種報道で、国土交通省が長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額(現行8000万円)を引き上げる方向で検討に入ったと報じられたのです。実現すればおよそ20年ぶりの見直し。東京23区の新築マンション平均価格が1億3000万円を超すなど、建築費が高騰し借入額も増える昨今では、住宅取得を考える方にとって非常に大きなニュースです。
そこで今回は、フラット35の融資限度額が引き上げられる背景とその見通しを、住宅ローン選びの観点から解説します。
変動金利上昇の背景と、固定金利ニーズの高まり
そもそも、なぜいま固定金利への関心が高まっているのでしょうか。それは、長く続いた日銀のマイナス金利政策が2024年3月に撤廃され、その後、政策金利の引き上げに連動して変動金利タイプの住宅ローン金利が上昇しているからです。
変動金利タイプの住宅ローンは、政策金利がマイナス0.1%だった2024年初頭には、0.3%を切るような超低金利の金融機関もありました。しかし現在(2025年11月時点)、政策金利はプラス0.5%。変動金利は金融機関によっては0.6%をかろうじて切る程度で、一般的には0.7~0.8%前後まで上昇しています。さらに早ければ12月、遅くとも年明けには日銀が政策金利を0.75%へ引き上げるとの見方もあり、そうなると変動金利タイプは1.0%の大台を超える可能性もあります。
こうした中で、借入時点で金利が確定する固定金利タイプの住宅ローンに注目が集まっているのです。
固定金利の動向と、長期金利上昇の背景
ただ、政策金利の引き上げとともに、固定金利タイプの住宅ローン金利も上昇しています。その背景にあるのが、長期金利(日本の10年モノ国債の利回り)の上昇です。
黒田前総裁の時代に始まった日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)は、当初0.25%を上限としていましたが、2023年には1.0%をめどに緩和し、2024年3月に政策自体を撤廃。その後、国債買入れの減額などもあり、現在(2025年11月7日)の長期金利は1.68%前後まで上昇しています。これに連動し、民間の全期間固定金利タイプは軒並み2%台後半に上昇しています。
民間金融機関では“長期固定離れ”も進む
さらに、金利が上がっているだけではありません。民間金融機関の中には、長期固定金利タイプの住宅ローンの取り扱いをやめる、または新規受付を停止する動きも出ています。実際にわたくし草野が見聞きしている東海地方の地銀・信金でも、立て続けに複数行が取り扱いを終了しました。
背景には、金利上昇で採算が合わなくなったことがあります。固定金利は「貸し出した時点の金利で長期固定」されるため、将来の調達金利が上がると金融機関の収益を圧迫します。このため、民間金融機関の「変動金利中心」へのシフトが進んでいるのです。
フラット35の金利はほぼ据え置き、割安感が拡大
こうした中で、民間が撤退する領域をカバーする公的ローンとしてのフラット35の存在意義が、あらためて見直されています。
注目すべきは、利上げ環境下でもフラット35の金利がほぼ据え置きとなっている点です。2025年11月の金利は年1.90%(最頻値)。民間の全期間固定金利が2%台後半まで上昇していることを考えると、フラット35の割安感が際立ちます。
👉 詳細: 2025年11月金利動向コラム
さらに、フラット35にはフラット35Sや子育てプラスなどの金利優遇制度があり、当初5年~10年間で最大年▲1.0%もの引き下げがあります。これは11月の金利でいえば、例えば当初5年間が0.90%、以降が1.90%となるということ。つまり、「低金利+固定金利+金利引下げ」という三拍子がそろっているのが、現在のフラット35です。このような背景で、わたくし草野のご相談においても、フラット35を検討する方が確実に増えています。
限度額引き上げが実現すれば、利用しやすさは格段に向上
今回の融資限度額引き上げの検討は、どんな人にメリットがあるのでしょうか。
代表的なケースを挙げると
- 都市部や人気エリアで土地+建物価格が8,000万円を超える世帯
- 二世帯住宅や高性能住宅など、建築費が高めの注文住宅を建てたい方
- 変動金利よりも安心を優先したい長期固定志向のファミリー層
東海エリアでも、名古屋市やその近郊では地価や建築費の高騰により、土地+建物で8,000万円を超えるケースが増えています。制度改正で限度額が引き上げられれば、こうした世帯でもフラット35を活用しやすくなるでしょう。
ただし、「借りられる=返せる」ではない
とはいえ、限度額の引き上げは「借入可能額の拡大」であって、「返済負担が軽くなる」わけではありません。特に固定金利タイプは、月々の返済が一定である代わりに、変動金利タイプより当初の返済額が大きくなりやすい特徴があります。
重要なのは、自分の家計の体力を冷静に見極めること。
そのために一番確実なのは、キャッシュフロー表(ライフプラン)を使い「借りても安心な金額」を算定することです。制度に合わせるのではなく、家計に合わせた住宅ローン選びこそが、後悔しない家づくりのカギといえます。
まとめ:時代は「固定金利回帰」へ。フラット35の動向に注目
金利が上がり、民間の固定型が縮小する中で、フラット35が再び脚光を浴びています。限度額の引き上げが実現すれば、制度としての利便性が一段と向上するでしょう。
ただし、「使いやすくなる=すべての人に最適」というわけではありません。次回は、これだけ魅力的なフラット35にもある“注意点と落とし穴”について、実際の相談事例を交えて解説します。どうぞお楽しみに。
📌 行動提案
- 制度改正を待つ間に、「キャッシュフロー表(ライフプラン)」を作成し、返済余力を確認しましょう。
- フラット35、民間の固定金利タイプ、変動金利タイプのトリプル比較を行い、自分の家計に最適な金利タイプを整理しておくのがお勧めです。
- 制度が実際に改正された際には、住宅会社・金融機関との打ち合わせで最新情報を必ず確認しましょう。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□