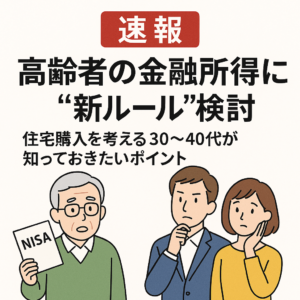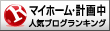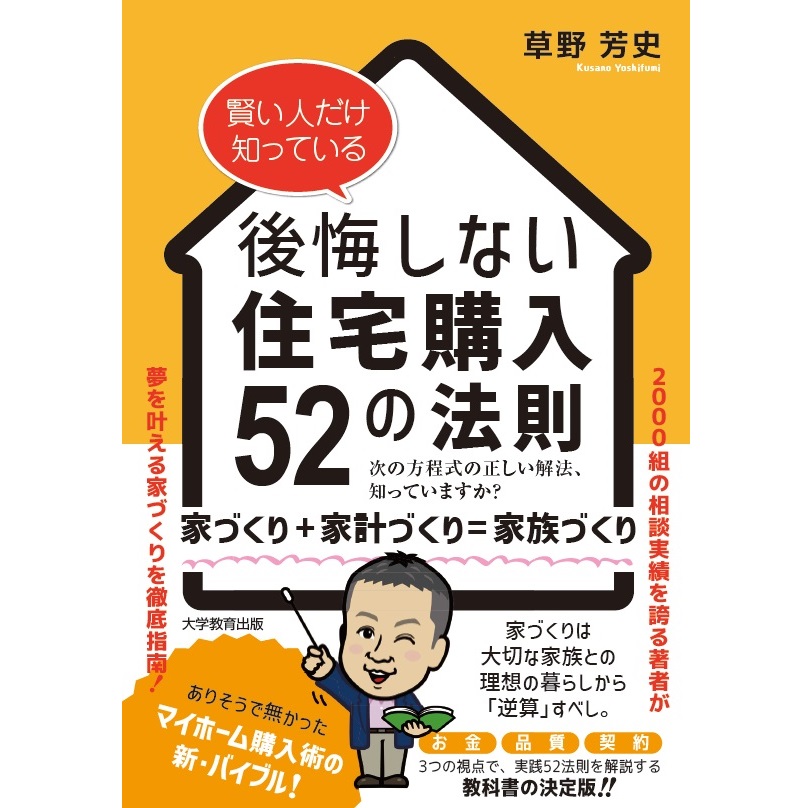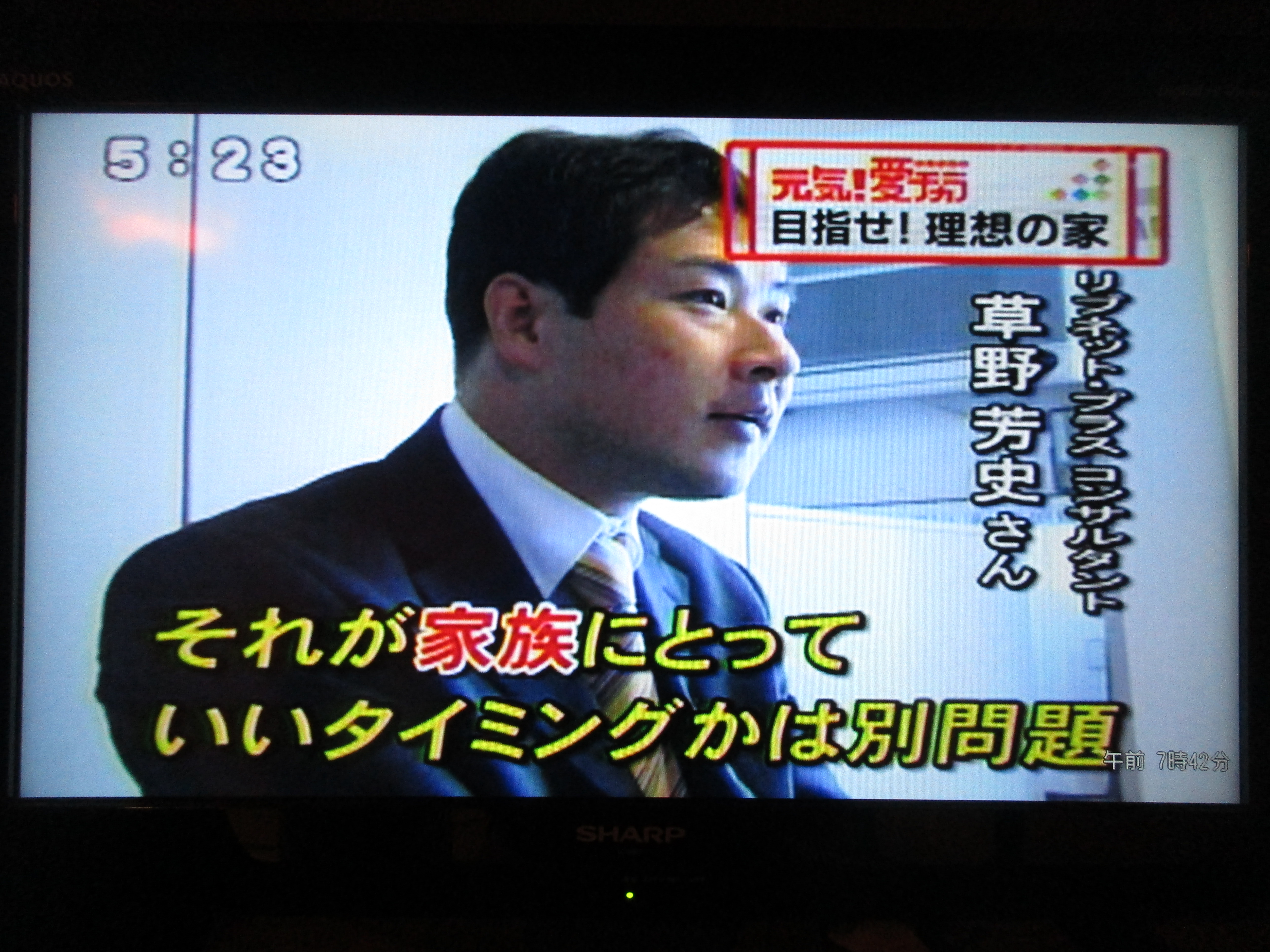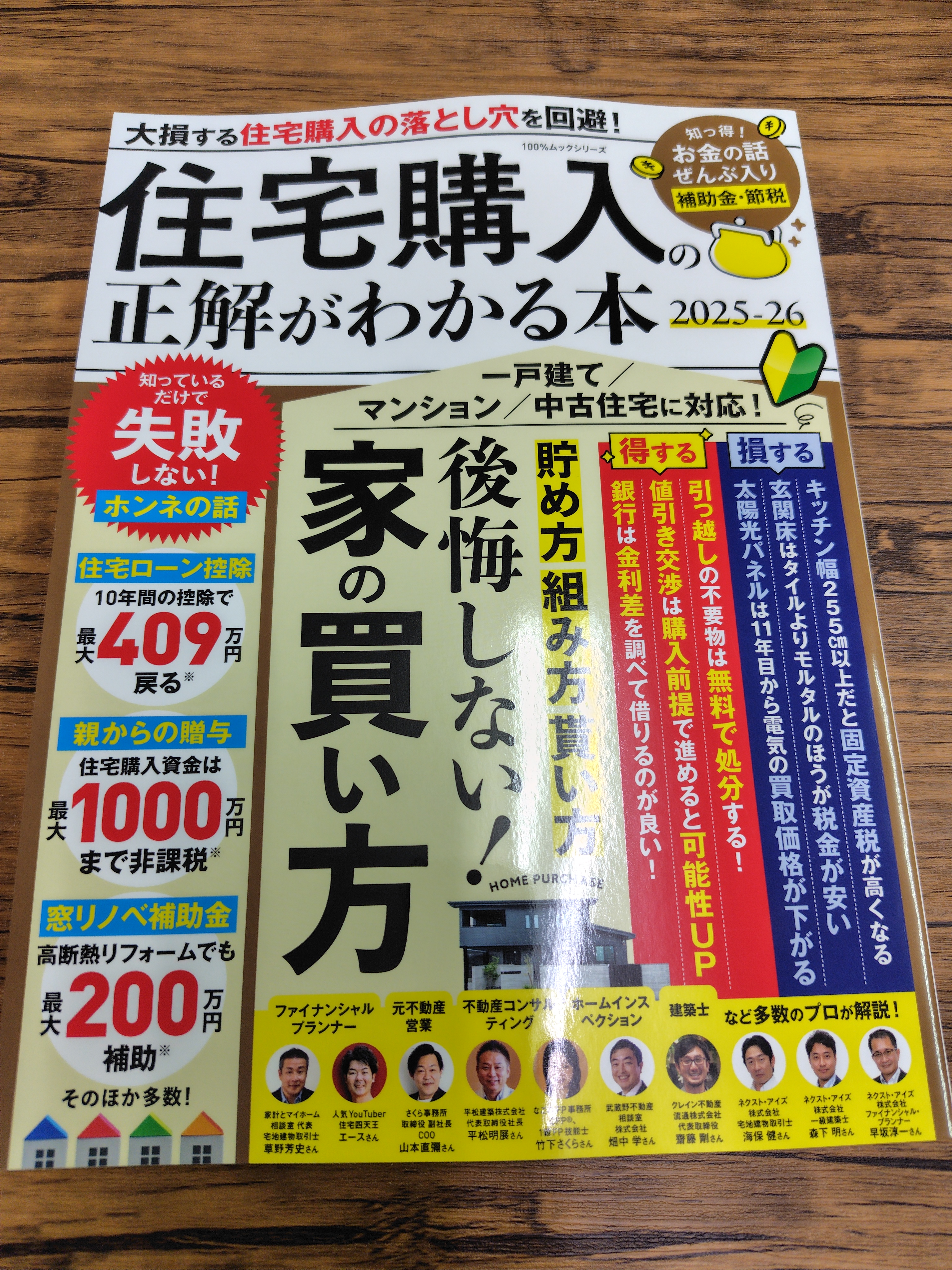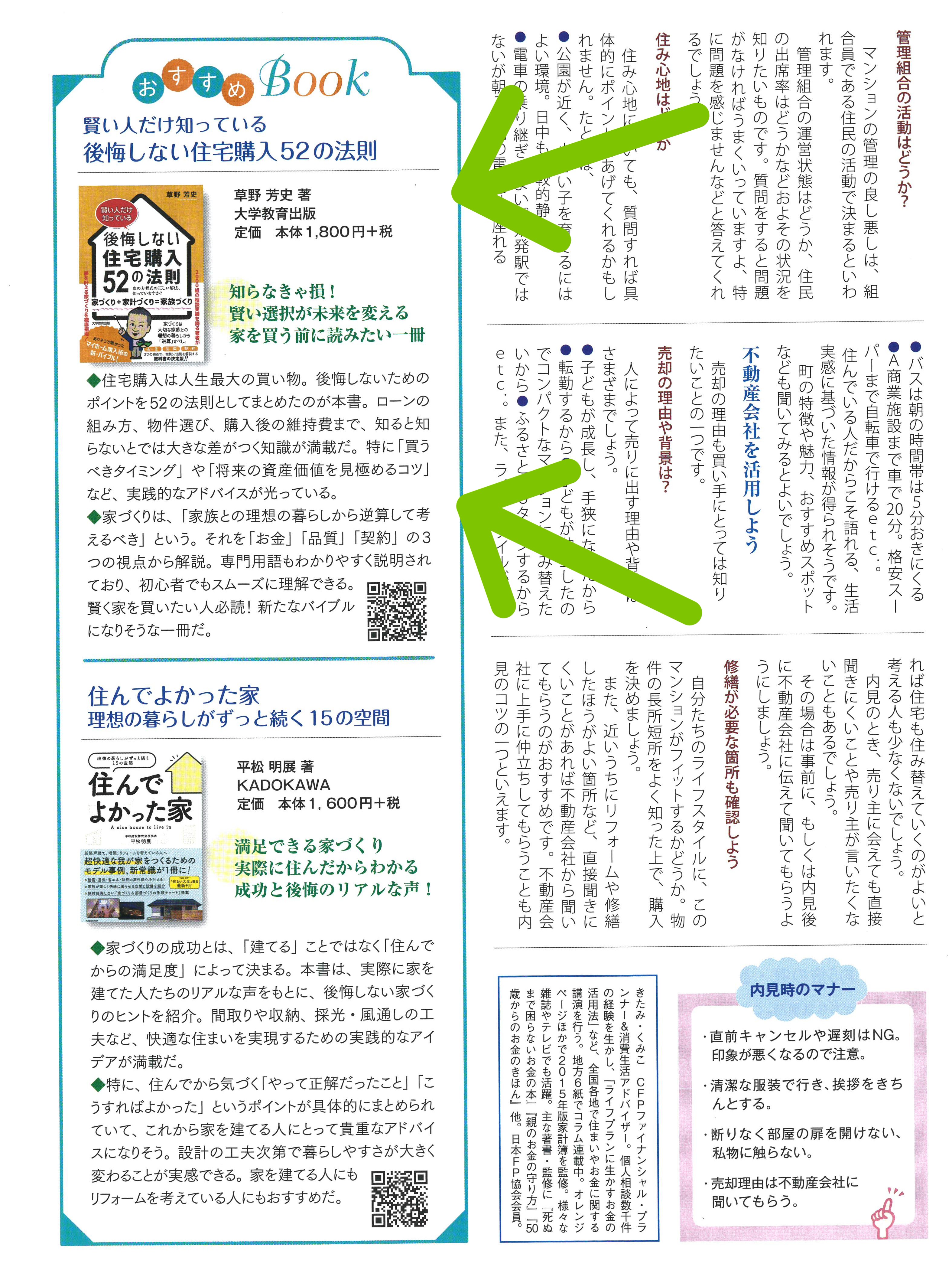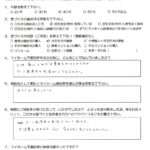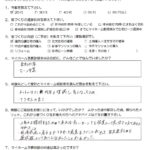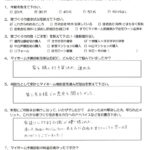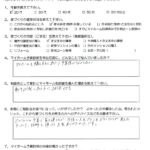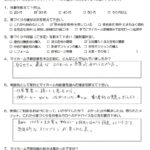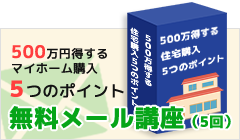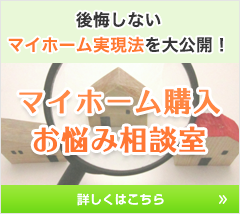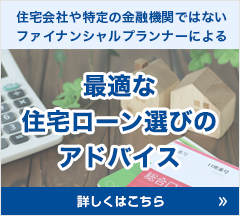本日11月19日付の日経新聞朝刊など、新聞各紙で「高齢者の金融所得に新ルール」との見出しが踊りました。政府・厚生労働省が、75歳以上の後期高齢者の医療保険料や窓口負担に、株式配当や譲渡益、預貯金の利子といった“金融所得”を反映させる方向で検討に入ったという内容です。
新NISAなどで投資運用を促進する政策が進むなかでのニュースだっただけに、最近NISAを始めた方のなかには、「え、運用したら医療費が上がるの?」「若い世代も対象になるの?」と“はしごを外された”ような気持ちになった方もいたかもしれません。結論から言えば、今回の動きは当面“75歳以上”が対象であり、現役世代の保険料や医療費がすぐに増えるわけではありません。
ただし、「長期的には自分の将来に関わる可能性がある」テーマですので、現行制度の仕組みや今回の動きの背景、そして今後の影響を整理していきます。
■現行制度では“75歳以上”と“75歳未満”で何が違う?
医療保険の基本構造をおさらい
制度を理解するために、まず医療保険の仕組みを簡単に整理しておきましょう。
1)75歳以上(後期高齢者医療制度)
- 医療費の自己負担割合は1~3割
- 判定基準は 住民税課税所得や年金収入
- 一方で 株式配当・譲渡益・預金利子=金融所得はほぼ反映されない
つまり、とても単純化すると「年金は反映されるが、金融所得は“見えない”扱いになっている」という制度のすき間があります。申告不要制度などにより金融所得が把握しにくく、制度上の公平性が課題視されてきました。
2)75歳未満(国保・協会けんぽ・組合健保)
こちらは仕組みがまったく異なります。
- 給与や事業所得をベースに保険料を算定
- 金融所得はそもそも対象外
- 今回の議論もここには波及していない
そのため、30~40代がいま受け取っている給与明細の保険料が変わることはありません。
■なぜ今「金融所得を把握する」議論が出てきたのか?
背景と政策の狙い
今回の議論は“突然の増税”ではなく、複数の背景が重なった結果といえます。
1)医療費・介護費が加速度的に増え続けている
後期高齢者の医療費は公費負担が大きく、制度の持続性が大きな課題になっています。
2)高齢者の金融資産の偏在
データを見ると、高齢世代ほど株式・預貯金・配当所得が多い構造があります。にもかかわらず、負担判定では“年金中心”というのが現状です。
3)「応能負担」=負担能力に応じた負担へ
年金収入が少なくても、金融資産を多く保有している世帯が一定数存在します。「負担能力がある人が適正に負担していないのでは」という問題意識があります。
4)マイナンバーで“金融所得を把握できる時代”に
マイナンバーと金融口座の紐づけ、法定調書の電子化が進み、「もう把握できるのだから、制度に反映しよう」という議論が出やすくなっています。
■30~40代には今すぐ影響はある?
“いまの生活”と“将来の家計”の2軸で整理
★短期的な影響はほぼゼロ
現時点で、
- 健康保険料
- 国民健康保険料
- 医療費の自己負担割合
これらが増えることはありません。また、
- NISA
- 投資信託
- 株式の配当
- 預金利子
これらが「今すぐ保険料に影響する」こともありません。
★中長期的には“老後の医療費負担”として影響しうる
ただし、将来75歳を迎えたときには
- 金融所得も含めて負担能力を判定
- 医療費や保険料が変動
- 老後の支出に影響
という可能性があります。
また、30~40代の親世代が影響を受ける場合、介護費や医療費負担が家計に跳ね返るケースも十分あり得ます。
■制度が若い世代にも広がる可能性は?
“ゼロではない”理由を冷静に解説
今回の制度は「75歳以上」を対象とした議論ですが、将来の方向性としては次の流れが考えられます。
- 医療・介護の財政はさらに厳しくなる
- 応能負担の考え方は全世代に及ぶ可能性
- マイナンバー制度で金融所得の把握は容易になりつつある
現行制度をすぐに変えるのは難しいものの、長期的には若年層にも波及する可能性が“ゼロではない”というのがファイナンシャルプランナーとしての見立てです。
■住宅購入を考える30~40代が今できる3つの備え
1)老後の医療・介護費を織り込んだ「ライフプラン(キャッシュフロー表)」をつくる
住宅ローン返済だけでなく、65歳以降の医療費・介護費をあらかじめ反映しておくことが重要です。
2)資産運用と将来の社会保険負担のバランスを見る
NISAは“増やすための器”ですが、将来「資産を持つ人の負担が増える」方向に制度が動く可能性もあります。偏りすぎず、家計全体でバランスを取りましょう。
3)親世代の資産・医療費の状況も把握する
親の医療・介護費を子世帯が支援するケースは珍しくありません。今回の議論が“親世代の負担”に影響する可能性もあります。
■まとめ
ショッキングな見出しに振り回されず、“家計の地図”で備える
今回の「高齢者の金融所得に新ルール」というニュースは、見出しだけ見るとショッキングですが、現役世代に直ちに影響するものではありません。
ただし、長期的に見ると
- 老後の医療費負担の変化
- 親世代の医療・介護費の負担
- 資産運用の位置づけ
など、将来のライフプランにじわりと関係してくるテーマです。
住宅取得と老後設計は、本来“セット”で考えるべきもの。制度の動きを正しく把握しながら、家計の将来予測地図であるライフプラン(キャッシュフロー表)を用いて備えることが大切です。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!
名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー
家計とマイホーム相談室 草野芳史
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□